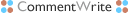東京どこに住む? 住所格差と人生格差 速水健朗 朝日新書 2016年

かつてないほどに、都市、特に東京への一極集中が続くと言われる世の中において、東京での暮らしはどうなっているのかを分析してみると、今までにない新たな法則が打ち出されてくる。それはすなわち、23区の皇居から5km圏内への人口集中と、そこから外れた地区の没落傾向である。そのような傾向が生まれた背景を分析するとともに、住む場所探しの最新トレンドに迫る。
「西高東低」と言われる東京の居住地人気は、長きにわたってのトレンドである。収入のある人々は武蔵野台地に開発された西側地区に高級住宅地を形成し、郊外の暮らしを謳歌した。しかし、近年、新たな暮らし方がトレンドとなりつつある。それは、都心への通勤負担の少なく、都心生活を謳歌しやすい地域、具体的には港区・千代田区・中央区といった、あまり住宅地としてのイメージがなかった地域や、山手線のやや東側にある通勤至便の地域に人が住み始めていることである。
本書では、そのような都市型生活を選択した人々や、あえて郊外生活を選択した人々の事例を紹介することを通して、住む場所の選択が生活に及ぼす影響についてまとめている。ここで紹介されるのはあくまで世の中の「強者」であろう。望めば高いお金を払っても住居を選べる人々だ。だから、これが世の中全体の傾向とは言えない部分もあるが、少なくとも世の中の上位階層の人々は、このようにして住居を選択しているということはわかる。
本書を読んでいると、住居による新たな格差社会を想像せずにはいられない。都市部への移動が不可能な人々は、地元を愛し、地元で十分と考える「ヤンキー経済」的な考えでもって自分の生活に納得していくしかないのか。
PR